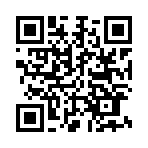2013年08月02日
プロ講師考(73)
『ビジネスパーソンは歴史がお好き』

ビジネスパーソンに歴史ネタは受ける。信長は「破壊」、秀吉は「創造」、家康は「継続」といった切り口で広げると興味を引く。戦国時代と幕末は認知度が高く伝わりやすい。歴史探訪の機会を得たら何かネタにならないか考えると良い、自分が見聞きしたものは説得力が増す。
⇒信長さん達の例は素人でもなんとなくわかる、歴史ってそういうものなのですね。それこそ人の一生がいっぱい詰まっているのですから重みがあり、人に伝わりやすいと思います。何か教訓的なものに結びつけられないか、そんなことを考えながら歴史に接しようと感じました。
ビジネスパーソンに歴史ネタは受ける。信長は「破壊」、秀吉は「創造」、家康は「継続」といった切り口で広げると興味を引く。戦国時代と幕末は認知度が高く伝わりやすい。歴史探訪の機会を得たら何かネタにならないか考えると良い、自分が見聞きしたものは説得力が増す。
⇒信長さん達の例は素人でもなんとなくわかる、歴史ってそういうものなのですね。それこそ人の一生がいっぱい詰まっているのですから重みがあり、人に伝わりやすいと思います。何か教訓的なものに結びつけられないか、そんなことを考えながら歴史に接しようと感じました。
2013年08月01日
プロ講師考(72)
『比喩・寓話を創る』

具体的事例を挙げることは大切だが、具体的事例の反対に位置する「比喩」「寓話」を用いるほうが効果的な場合もある。「もしもウサギにコーチがいたら」のようにたとえ話を用いると興味を引く。若い部下をウサギにたとえてやる気を出させる方法を解説している。書籍もこのパタンが売れる。
⇒私のメンターさんはこの「たとえ話」が非常に上手です。どうしたらそうなれるか彼に聞いたところ、「日々物事を観察しその裏にどんなことが隠れているか、何を物語っているかを考えストックしておくと、将来それを使える時が来る」との答えでした。こころしていきたいです。
具体的事例を挙げることは大切だが、具体的事例の反対に位置する「比喩」「寓話」を用いるほうが効果的な場合もある。「もしもウサギにコーチがいたら」のようにたとえ話を用いると興味を引く。若い部下をウサギにたとえてやる気を出させる方法を解説している。書籍もこのパタンが売れる。
⇒私のメンターさんはこの「たとえ話」が非常に上手です。どうしたらそうなれるか彼に聞いたところ、「日々物事を観察しその裏にどんなことが隠れているか、何を物語っているかを考えストックしておくと、将来それを使える時が来る」との答えでした。こころしていきたいです。
2013年07月31日
プロ講師考(71)
『懇親会では飲み過ぎ厳禁』

終了後に懇親会に誘われることがあるが、その場での醜態で評判を下げてしまう講師がほんとうにいる。当日の聴講者をけなしたりライバル講師の悪口を言ったりして自分の価値を下げてしまう。酒での失態は講師の評判以上に早く広がってしまうもの。
⇒下戸の私にはまず心配はありません。お酒を飲めないのは何かと不利なことが多いのですが、上記のような事態を心配しなくて良いのは有利です。ですが、まだ懇親会に呼ばれるほどの経験はなく、今後の注意事項として頭に入れておきたいです。
終了後に懇親会に誘われることがあるが、その場での醜態で評判を下げてしまう講師がほんとうにいる。当日の聴講者をけなしたりライバル講師の悪口を言ったりして自分の価値を下げてしまう。酒での失態は講師の評判以上に早く広がってしまうもの。
⇒下戸の私にはまず心配はありません。お酒を飲めないのは何かと不利なことが多いのですが、上記のような事態を心配しなくて良いのは有利です。ですが、まだ懇親会に呼ばれるほどの経験はなく、今後の注意事項として頭に入れておきたいです。
2013年07月30日
プロ講師考(70)
『講演中に携帯電話を見るな!』

講演中に頻繁に携帯電話を見る講師が実際にいた。腕時計の代わりに携帯を見るのが習慣だったらしいが、聴講者はそうは受け取らない。メールや着信を気にしているように見えてしまう。講演中に講師のカバンの中で呼び出し音が鳴るハプニングも。電源offが原則である。
⇒最近は携帯電話のない日常生活は考えにくい。それだけ身近になっているからこそ扱いには注意が必要だということでしょう。実際に私もマナーモードにするのを忘れ、話している最中に呼び出し音が鳴ってしまい焦ったことがあります。過ちは繰り返さないようにします。
講演中に頻繁に携帯電話を見る講師が実際にいた。腕時計の代わりに携帯を見るのが習慣だったらしいが、聴講者はそうは受け取らない。メールや着信を気にしているように見えてしまう。講演中に講師のカバンの中で呼び出し音が鳴るハプニングも。電源offが原則である。
⇒最近は携帯電話のない日常生活は考えにくい。それだけ身近になっているからこそ扱いには注意が必要だということでしょう。実際に私もマナーモードにするのを忘れ、話している最中に呼び出し音が鳴ってしまい焦ったことがあります。過ちは繰り返さないようにします。
2013年07月26日
プロ講師考(69)
『常連ばかりの飲み屋には行きたくない』

固定ファンを大切にするあまり、新規客が入りにくい状態にならないような注意が必要。ブログの読者しかわからないネタを前提となる話抜きで語るべきではない。講師が何者かわからないで参加している聴講者でも惹きつけるのがプロ講師である。
⇒そのような講師の世界もあるものなのかと感じます。第一どうせ講師をやるからには常に新しい方に聞いてもらいたい、少しでも多くの人にコンテンツを伝えたいのが心情だと考えます。結果としてブログの内容を知っている方だったら嬉しく感じられるはず。
固定ファンを大切にするあまり、新規客が入りにくい状態にならないような注意が必要。ブログの読者しかわからないネタを前提となる話抜きで語るべきではない。講師が何者かわからないで参加している聴講者でも惹きつけるのがプロ講師である。
⇒そのような講師の世界もあるものなのかと感じます。第一どうせ講師をやるからには常に新しい方に聞いてもらいたい、少しでも多くの人にコンテンツを伝えたいのが心情だと考えます。結果としてブログの内容を知っている方だったら嬉しく感じられるはず。
2013年07月25日
プロ講師考(68)
『精神世界はほどほどに・・・』

読書やセミナー等、幅広く勉強をしている人が行き着くのが精神世界。しかしこれはかなり好き嫌いが分かれる。一部では聴講者がひいてしまい、宗教や一部の悪評な自己啓発セミナーと誤解されることがある。多少は入れても断定的にならないのが良い。
⇒私はまだこのような系統の話を聴いたことが無いのでぴんと来ません。しかし数ある講演会にはあっても不思議ではない、何せ言論の自由が保障されている国なのですから。関心の無い者には気にすることではありません。
読書やセミナー等、幅広く勉強をしている人が行き着くのが精神世界。しかしこれはかなり好き嫌いが分かれる。一部では聴講者がひいてしまい、宗教や一部の悪評な自己啓発セミナーと誤解されることがある。多少は入れても断定的にならないのが良い。
⇒私はまだこのような系統の話を聴いたことが無いのでぴんと来ません。しかし数ある講演会にはあっても不思議ではない、何せ言論の自由が保障されている国なのですから。関心の無い者には気にすることではありません。
2013年07月24日
プロ講師考(67)
『差別用語にご注意を』

日常用語には多くの差別用語が含まれる。これを知らずに使ってしまうと叱咤激励のつもりでいったことを問題視されて謝罪した講師もいる。女性蔑視や外国人差別等々うっかりでは済まされない場合もある。過度の下ネタもセクハラといわれることもあり要注意。
⇒ちょっと調べてみたところ、なるほど色々あるものです。身分差別、民族差別、身障者差別など。その中で最も多いのが職業差別用語のようです。なるほど言われてみれば差別していると感じるもの、気を付けないと。講師に勉強はつきものです。
日常用語には多くの差別用語が含まれる。これを知らずに使ってしまうと叱咤激励のつもりでいったことを問題視されて謝罪した講師もいる。女性蔑視や外国人差別等々うっかりでは済まされない場合もある。過度の下ネタもセクハラといわれることもあり要注意。
⇒ちょっと調べてみたところ、なるほど色々あるものです。身分差別、民族差別、身障者差別など。その中で最も多いのが職業差別用語のようです。なるほど言われてみれば差別していると感じるもの、気を付けないと。講師に勉強はつきものです。
2013年07月23日
プロ講師考(66)
『講演中の売り込みを目的にしない』

ノウハウの触り部分を連発するのはいただけない。そのような目次みたいな講演では、聴講者は消化不良になる。それより二、三のノウハウに絞って深く公開するほうが印象は良い。依頼を受けて講演する場合はその時間内で一定の簡潔が必要。
⇒講演により自分自身をPRして売り込むことはご法度ということ。確かに聴講者は講師の話すコンテンツを聞いて何かを得たいと思って集まってくる。そこで自己の売り込みをされたのではたまらない、相手の身になればすぐにわかることです。
ノウハウの触り部分を連発するのはいただけない。そのような目次みたいな講演では、聴講者は消化不良になる。それより二、三のノウハウに絞って深く公開するほうが印象は良い。依頼を受けて講演する場合はその時間内で一定の簡潔が必要。
⇒講演により自分自身をPRして売り込むことはご法度ということ。確かに聴講者は講師の話すコンテンツを聞いて何かを得たいと思って集まってくる。そこで自己の売り込みをされたのではたまらない、相手の身になればすぐにわかることです。
2013年07月22日
プロ講師考(65)
『控え室も見られている』

講師にとって主催者の評判は生命線である。講演で指導していることをできていない姿を見せてはいけない。控え室で態度が悪かったという評判は内容が良かったという情報より早く広まる。控え室で腰を低くしておき、講演が始まれば一切謙遜せずに自信満々というギャップは好ましい。
⇒「公と私」とよく分けられますが、「公」の中でも控え室と講演の場は分けられる。後者が本当の公であるのに対し、前者は一部公の場。前者を大切にしてふるまわないと一流の講師としては認められないということでしょう。場数を踏んで実感したいものです。
講師にとって主催者の評判は生命線である。講演で指導していることをできていない姿を見せてはいけない。控え室で態度が悪かったという評判は内容が良かったという情報より早く広まる。控え室で腰を低くしておき、講演が始まれば一切謙遜せずに自信満々というギャップは好ましい。
⇒「公と私」とよく分けられますが、「公」の中でも控え室と講演の場は分けられる。後者が本当の公であるのに対し、前者は一部公の場。前者を大切にしてふるまわないと一流の講師としては認められないということでしょう。場数を踏んで実感したいものです。
2013年06月28日
プロ講師考(64)
『緊張はエネルギー』

セミナー講師に適度の緊張は必要、緊張を和らげるために、日々、情報収集や聴講者分析を怠らないこと。講師の適度な緊張は聴講者にリアリティーを感じさせる。十分な準備をしない緊張は困るが、いつまでも緊張感を持ち続けることは継続的人気講師への鍵である。
⇒「緊張」が「エネルギー」になるのは理想的。一般的には緊張により言いたいことが言えなかったり、話し方が不自然になったりする。場数を踏めば理想に近づくのでしょう。そのためには慣れの意識を排除し、同じネタでも常に新鮮な気持ちで話すべきだと思います。
セミナー講師に適度の緊張は必要、緊張を和らげるために、日々、情報収集や聴講者分析を怠らないこと。講師の適度な緊張は聴講者にリアリティーを感じさせる。十分な準備をしない緊張は困るが、いつまでも緊張感を持ち続けることは継続的人気講師への鍵である。
⇒「緊張」が「エネルギー」になるのは理想的。一般的には緊張により言いたいことが言えなかったり、話し方が不自然になったりする。場数を踏めば理想に近づくのでしょう。そのためには慣れの意識を排除し、同じネタでも常に新鮮な気持ちで話すべきだと思います。
2013年06月27日
プロ講師考(63)
『聴き手の決定権』

情報の意味、内容を決定する権利は聴き手が持つ。誤解を招かないようにするには、キーワードやセンテンスは短く簡潔にする。結論を先に話す「演繹法」を使い、最後に改めて結論を繰り返すことが必要。聴き手の質が悪いから講演が失敗したなどと間違っても言ってはならない。
⇒いくら講師が良い話をしたつもりになっても、聴講者が満足しないと意味がない。講演が良かったかどうかは聴く側が決めるのは明らか。「結論を先に言う」は論理的思考においても大切なこと、結論に引き続きその根拠を話せば聴講者は納得しやすいと思います。
情報の意味、内容を決定する権利は聴き手が持つ。誤解を招かないようにするには、キーワードやセンテンスは短く簡潔にする。結論を先に話す「演繹法」を使い、最後に改めて結論を繰り返すことが必要。聴き手の質が悪いから講演が失敗したなどと間違っても言ってはならない。
⇒いくら講師が良い話をしたつもりになっても、聴講者が満足しないと意味がない。講演が良かったかどうかは聴く側が決めるのは明らか。「結論を先に言う」は論理的思考においても大切なこと、結論に引き続きその根拠を話せば聴講者は納得しやすいと思います。
2013年06月26日
プロ講師考(62)
『休憩は誰のため?』

120分を超える研修では休憩が必要。長いとだれるのでせいぜい10分。休憩明けには集中力が途切れるので改めてつかみネタが必要になる。参加型ゲーム等で頭をリフレッシュしてもらうのも良い。休憩は講師のためではなく、聴講者に効果的に学んでもらうためにとる。
⇒小中学校の授業時間が1時間未満だったものが高校や大学では長くなった、でも2時間が上限。人間の生理的欲求を満たさずに事を進めることは難しい。大切なのは流れの維持、せっかく盛り上げた聴講者の意識を休憩で下げてしまわないようにしたいです。
120分を超える研修では休憩が必要。長いとだれるのでせいぜい10分。休憩明けには集中力が途切れるので改めてつかみネタが必要になる。参加型ゲーム等で頭をリフレッシュしてもらうのも良い。休憩は講師のためではなく、聴講者に効果的に学んでもらうためにとる。
⇒小中学校の授業時間が1時間未満だったものが高校や大学では長くなった、でも2時間が上限。人間の生理的欲求を満たさずに事を進めることは難しい。大切なのは流れの維持、せっかく盛り上げた聴講者の意識を休憩で下げてしまわないようにしたいです。
2013年06月25日
プロ講師考(61)
『配布資料のタイミングの見極め』

講演の最初にレジメと一緒に読み物を配るのは失敗のもと。講演は講師の表情やゼスチャーを見ながら聴くことで内容が伝わる。詳細資料をつける際は必要なタイミングか終了後に渡すのが良い。講演中は講師のパフォーマンスに集中してもらうほうが聴講者の心に響く。
⇒確かに自分が話を聴く場合を考えると、資料を読まないと講師の話が理解できないのかと思って講演中に読む場合があります。ここで述べられているように、講師は話の内容以外に話し方、パフォーマンスで聴講者に訴えることを心がけるべきでノイズは入れないほうが良い。
講演の最初にレジメと一緒に読み物を配るのは失敗のもと。講演は講師の表情やゼスチャーを見ながら聴くことで内容が伝わる。詳細資料をつける際は必要なタイミングか終了後に渡すのが良い。講演中は講師のパフォーマンスに集中してもらうほうが聴講者の心に響く。
⇒確かに自分が話を聴く場合を考えると、資料を読まないと講師の話が理解できないのかと思って講演中に読む場合があります。ここで述べられているように、講師は話の内容以外に話し方、パフォーマンスで聴講者に訴えることを心がけるべきでノイズは入れないほうが良い。
2013年06月21日
プロ講師考(60)
『聴講者への逆質問は「ノリ」で選ぶ』

聴講者への逆質問をする双方向型は効果がある。ノリの良さそうな人を選び恥をかかせないことがポイント。挙手を誘う場合は多少会場が和んだ状態でやるべき。聴く側の集中力が途絶えないように双方向型を用いて聴講者を巻き込みながら展開させることは効果的。
⇒コミュニケーションは発する側と受ける側があって成立するのですから、講演においても聴く側を巻き込むことが重要。その際質問に答えさせるのは効果的な方法ですが、タイミングや相手の指定は非常に難しい。外してしまった時の対応を考えてそのスキルを使うべきです。
聴講者への逆質問をする双方向型は効果がある。ノリの良さそうな人を選び恥をかかせないことがポイント。挙手を誘う場合は多少会場が和んだ状態でやるべき。聴く側の集中力が途絶えないように双方向型を用いて聴講者を巻き込みながら展開させることは効果的。
⇒コミュニケーションは発する側と受ける側があって成立するのですから、講演においても聴く側を巻き込むことが重要。その際質問に答えさせるのは効果的な方法ですが、タイミングや相手の指定は非常に難しい。外してしまった時の対応を考えてそのスキルを使うべきです。
2013年06月20日
プロ講師考(59)
『質疑の回答が悪いと一気に評価が下がる』

適切な質問が出たのに講師がピント外れの回答をするケースがある。基本は答えを先に言って後で根拠をいうのがベスト。質問の意味が分かりにくい場合は質問を要約して確認後回答すると他の聴講者にもやさしいものになる。具体的な事例を織り交ぜると説得力がでる。
⇒文書の書き方講座では「結論を先に述べる」とお教えしています。まず質問に対する最終的な答えをスパッと表明し、それからその理由について話せば、聴講者は理解してくださると思います。事例を使って説明するのはどのタイミングでも大切、日頃から事例をたくさんストックせねば!
適切な質問が出たのに講師がピント外れの回答をするケースがある。基本は答えを先に言って後で根拠をいうのがベスト。質問の意味が分かりにくい場合は質問を要約して確認後回答すると他の聴講者にもやさしいものになる。具体的な事例を織り交ぜると説得力がでる。
⇒文書の書き方講座では「結論を先に述べる」とお教えしています。まず質問に対する最終的な答えをスパッと表明し、それからその理由について話せば、聴講者は理解してくださると思います。事例を使って説明するのはどのタイミングでも大切、日頃から事例をたくさんストックせねば!
2013年06月19日
プロ講師考(58)
『質疑応答にはパターンがある』

質疑応答によってせっかくの講演が台無しになることがある。質問が出ない、質問でなく自分の意見を言う人がいる、自分にしか関係の無い質問をする人がいる、等々。個々に対応のコツを覚えておくと良い。質疑応答は計算できないので対応が難しい、大切なことは時間枠を守ること。
⇒上記のような質問者には講演会で良く遭遇し、聴講者の一人として不快に感じることがあります。私が質問するときは聴衆を代表して、”皆さんこんなこと聞きたいだろうな”と思うことを質問させていただきます。でも良識ある質問者に期待しないほうが良さそうです。
質疑応答によってせっかくの講演が台無しになることがある。質問が出ない、質問でなく自分の意見を言う人がいる、自分にしか関係の無い質問をする人がいる、等々。個々に対応のコツを覚えておくと良い。質疑応答は計算できないので対応が難しい、大切なことは時間枠を守ること。
⇒上記のような質問者には講演会で良く遭遇し、聴講者の一人として不快に感じることがあります。私が質問するときは聴衆を代表して、”皆さんこんなこと聞きたいだろうな”と思うことを質問させていただきます。でも良識ある質問者に期待しないほうが良さそうです。
2013年06月18日
プロ講師考(57)
『自意識過剰と間違った気遣い』

声の大きさに自信があるとマイクを使わずに話すのはNG、高いところからは失礼と舞台から降りて話すのもNG。前者は会場の条件を考えると聞きにくいこともありうる、後者は後ろから見えなくなってしまう。ということで間違った気遣いやパフォーマンスは結果として不評を買う。
⇒まだそれだけの立派な環境下で話したことが無いので、ちょっと実感がわきませんがこころしたいと思います。「僭越ながら・・・」的にへりくだる点も同様で、そのような表現はせいぜい1回にしたい。多分これを繰り返すと聴講者はシラケてしまうでしょう。
声の大きさに自信があるとマイクを使わずに話すのはNG、高いところからは失礼と舞台から降りて話すのもNG。前者は会場の条件を考えると聞きにくいこともありうる、後者は後ろから見えなくなってしまう。ということで間違った気遣いやパフォーマンスは結果として不評を買う。
⇒まだそれだけの立派な環境下で話したことが無いので、ちょっと実感がわきませんがこころしたいと思います。「僭越ながら・・・」的にへりくだる点も同様で、そのような表現はせいぜい1回にしたい。多分これを繰り返すと聴講者はシラケてしまうでしょう。
2013年06月17日
プロ講師考(56)
『どんな講演でも寝る人は寝る』

初めから寝るつもりで来ている輩もいる。寝ている人や携帯電話を鳴らす人がいても講師が集中力をなくしてはプロとは言えない。そのような人にエネルギーをさくのはやめるべき。但し寝ている人が異常に多いとしたら講師に問題がある、対策を講じる必要がある。
⇒なるほど、ある意味開き直りが必要と解釈しました。特に昼食後の時間帯は寝るなと言うのが無理かもしれません。寝ていて損をするのは本人なので、事前にその点を伝えるようにしています。しかし理想は睡魔をものともしない内容の面白さ、その領域に達してみたいです。
初めから寝るつもりで来ている輩もいる。寝ている人や携帯電話を鳴らす人がいても講師が集中力をなくしてはプロとは言えない。そのような人にエネルギーをさくのはやめるべき。但し寝ている人が異常に多いとしたら講師に問題がある、対策を講じる必要がある。
⇒なるほど、ある意味開き直りが必要と解釈しました。特に昼食後の時間帯は寝るなと言うのが無理かもしれません。寝ていて損をするのは本人なので、事前にその点を伝えるようにしています。しかし理想は睡魔をものともしない内容の面白さ、その領域に達してみたいです。
2013年06月14日
プロ講師考(55)
『できないテーマは断る』

講師として少し知名度が上がってくると、さまざまなテーマでの依頼が来る。このとき何でも受けてしまうのは避けるべき。一度内容が浅いと指摘された講師は、本来の得手テーマであっても浅いのではと思われてしまう。「得手に帆を上げる」はプロ講師で成功するためにとても大切な信条である。
⇒まだとてもその領域には達していませんが、もしもそのような状況になったら気をつけたいと思います。ラーメン屋さんでカレーライスがメニューにあるとこだわりのラーメンさえも二流に感じてしまう、やはり特化したほうが強みが強調されるのでしょう。
講師として少し知名度が上がってくると、さまざまなテーマでの依頼が来る。このとき何でも受けてしまうのは避けるべき。一度内容が浅いと指摘された講師は、本来の得手テーマであっても浅いのではと思われてしまう。「得手に帆を上げる」はプロ講師で成功するためにとても大切な信条である。
⇒まだとてもその領域には達していませんが、もしもそのような状況になったら気をつけたいと思います。ラーメン屋さんでカレーライスがメニューにあるとこだわりのラーメンさえも二流に感じてしまう、やはり特化したほうが強みが強調されるのでしょう。
2013年06月13日
プロ講師考(54)
『「毒舌」の明と暗』

毒舌を売り物にしている講師は、当たり障りのない話をする講師よりインパクトがあり、痛快な印象を与える。ビジネス系講演会では「毒舌講師」が少ないので、うまくブランディングすれば人気講師になれる可能性が高い。但し毒舌は度を越すと聴いている側が不愉快になるので注意。
⇒どう考えても私は”当たり障りのない話をする講師”サイドにいるので、毒舌が使えたら羨ましいと思います。私の目指すのは「ユーモアのある毒」、毒舌の中に皮肉や風刺などユーモラスさがあれば笑いが起こる。さしずめ、綾小路きみまろさんのようなトークができたら最高です。
毒舌を売り物にしている講師は、当たり障りのない話をする講師よりインパクトがあり、痛快な印象を与える。ビジネス系講演会では「毒舌講師」が少ないので、うまくブランディングすれば人気講師になれる可能性が高い。但し毒舌は度を越すと聴いている側が不愉快になるので注意。
⇒どう考えても私は”当たり障りのない話をする講師”サイドにいるので、毒舌が使えたら羨ましいと思います。私の目指すのは「ユーモアのある毒」、毒舌の中に皮肉や風刺などユーモラスさがあれば笑いが起こる。さしずめ、綾小路きみまろさんのようなトークができたら最高です。